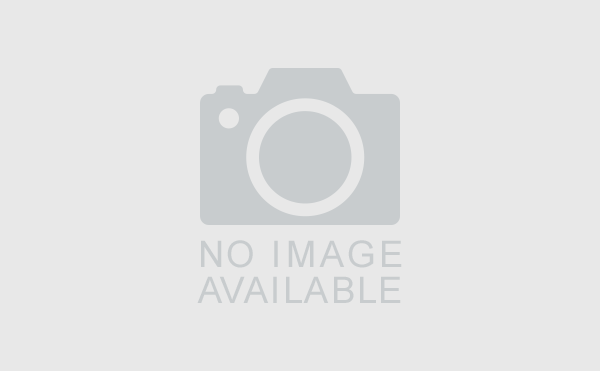認知行動療法の歴史とそれらの概要
CBTは、1950年代半ばにAlbert Ellisが合理情動行動療法(REBT)を提唱したことに始まり、その後1960年代にAaron Beckが認知療法(CT)を確立しました 。1970〜80年代には、Lewinsohnらの憂うつモデルを起源とする行動活性化や、Youngによるスキーマ療法が生まれ、認知と行動の統合が進みました 。さらに1980〜90年代以降、「第三の波(Third-Wave)」と呼ばれるDBT、ACT、MBCT、メタ認知療法などが登場し、マインドフルネスや受容、メタ認知といった新たな視点が加わりました 。
## 起源:REBTと認知療法の創始
1. 合理情動行動療法(REBT)
- 提唱者・年代:Albert Ellis(1955年頃) 。
- 概要:クライエントの非合理的信念を直接的に認知・行動レベルで修正し、情動変化を促す。REBTにより「思考→感情→行動」の因果ルートが注目されるようになった 。
2. 認知療法(CT)
- 提唱者・年代:Aaron Beck(1960年代) 。
- 概要:抑うつ患者の自動思考やスキーマ(認知の枠組み)を概念化し、認知再構成法によって思考パターンを修正。うつや不安など多くの障害で有効性が示された 。
行動的技法の統合
3. 行動活性化モデル(BA)
- 起源:Peter Lewinsohnらによる1970年代の抑うつ行動モデルを基盤とする 。
- 概要:うつ状態では行動の回避・停滞が起こり、それを変えることで気分も改善するとする。行動の活性化を中心に据え、認知技法と併用されることが多い。
4. スキーマ療法
- 提唱者・年代:Jeffrey E. Young(1980–90年代) 。
- 概要:幼少期から形成された「原始的スキーマ」が成人後の不適応行動を引き起こすとし、認知・行動・情動・関係性すべての側面からスキーマを修正するアプローチ 。
第三の波(Third-Wave CBT)
5. 弁証法的行動療法(DBT)
- 提唱者・年代:Marsha Linehan(1991年初版論文) 。
- 概要:境界性人格障害の自傷・自殺企図リスクに応えるため、受容(Dialectics)と変化(Behavioral Change)を統合。マインドフルネス、感情調整、対人関係スキルなど複数技能を体系的に教示 。
6. アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)
- 提唱者・年代:Steven C. Hayes(1980年代後半) 。
- 概要:思考や感情を変えるのではなく、受容と「今ここ」の行動へのコミットメントを重視。関係性フレーム理論(RFT)を基礎とする 。
7. マインドフルネス認知療法(MBCT)
- 提唱者・年代:Zindel Segal, Mark Williams, John Teasdale(1990年代前半) 。
- 概要:Jon Kabat-ZinnのMBSRを統合し、再発抑うつ予防に特化。マインドフルな「気づき」を通じて自動思考に距離を置く 。
8. メタ認知療法(MCT)
- 提唱者・年代:Adrian Wells(1990年頃 ATT開発) 。
- 概要:思考そのものではなく思考への注意やメタ認知信念を修正。ATT(注意訓練技法)などを通じ、反すうや回避的注意を減らす 。
モデル間の関係図(ASCIIフロー)
[REBT (Ellis, 1955)]
↓
[認知療法 CT (Beck, 1960s)]
↙ ↘
[BAモデル] [スキーマ療法]
↘ ↙
[第三の波 CBT]
┌───────────────┐
│ DBT ACT MBCT MCT │
└───────────────┘
- REBT→CT:思考の「非合理性」から「自動思考・スキーマ」への焦点移動 。
- CT→BA/スキーマ:行動活性化や深層スキーマの概念を統合し、認知と行動の双方向性を強化 。
- 第三の波:マインドフルネス(MBCT/DBT)、受容(ACT)、メタ認知(MCT)という新たな枠組みを取り込み、CBTの適用領域と技法を拡大 。
以上がCBTの歴史的発展と主要モデルの関連図です。ご質問やさらに深掘りしたいモデルがあればお知らせください。